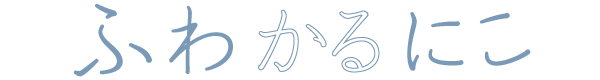福岡県宗像市のリラクゼーションサロン「ふわかるにこ」です。
当サロンの庭には青ジソも赤シソもたくさん自生しており、種をまかなくても毎年元気に生い茂っています。
以前は薬味として少し食べる程度でしたが、今では普通の葉物野菜と同じように、サラダやお浸し、炒め物にしてたくさん頂くようになりました。
「シソ」と言えば、青ジソの葉の部分である「大葉」だけでなく、花や実、赤シソも含まれます。
この記事では主に大葉の部分について、含まれる栄養成分と効能をご紹介します。
大葉の栄養成分一覧
大葉の栄養成分については、文部科学省が公表している『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』に掲載されています。
それを基に作成した、大葉の栄養成分一覧表がこちらです。
特に多く含まれている成分を太字で示しています。
- エネルギー(32kcal)
- 水分(86.7g)
- タンパク質(3.9g)
- 脂質(0.1g)
- 炭水化物(7.5g)
- 食物繊維(7.3g)
- ナトリウム(1mg)
- カリウム(500mg)
- カルシウム(230mg)
- マグネシウム(70mg)
- リン(70mg)
- 鉄(1.7mg)
- 亜鉛(1.3mg)
- 銅(0.20mg)
- マンガン(2.01mg)
- ヨウ素(6μg)
- セレン(1μg)
- クロム(2μg)
- モリブデン(30μg)
- β-カロテン当量(11000μg)
- ビタミンB1(0.13mg)
- ビタミンB2(0.34mg)
- ビタミンB6(0.19mg)
- ビタミンC(26mg)
- ビタミンE(3.9mg)
- ビタミンK(690μg)
- 葉酸(110μg)
- パントテン酸(1.00mg)
- ナイアシン(1.0mg)
- ビオチン(5.1μg)
大葉にはこの他にも、「ペリルアルデヒド」という香りの成分や、「ロズマリン酸」というポリフェノールなどが含まれており、防腐作用やアレルギー抑制などさまざまな効能を期待できます。
また、青ジソも赤シソも成分量に大差はありませんが、赤シソには赤い色素成分である「アントシアニン」が含まれています。
大葉に多く含まれる成分と効能

β-カロテン当量(11000 μg)
β-カロテン当量とは、体内でビタミンAに変換されて作用するカロテノイドの量を表したもので、大葉には100g当たり11000μgも含まれています。
これはカロテノイドの語源でもあるニンジンよりも多く、野菜の中では一番です。
ビタミンAには目や皮膚の粘膜を健康に保ったり、抵抗力を強めたりする働きがあり、健康維持や免疫力アップ、美肌への効果効能も期待できます。
ビタミンB2(0.34mg)
ビタミンB2はほとんどの栄養素の代謝に関わっている成分で、身体全体の健康維持に効果的です。
アルコールを分解する作用もあり、お酒を飲む時に大葉をつまむと二日酔い予防にもなります。
タンパク質の合成をサポートして、皮膚、髪、爪などの細胞の再生にも寄与するため、美容効果も期待できます。
お肉やお魚をシソで巻いて食べるのはもちろん、大葉自体にもタンパク質が100g当たり3.9gと、葉物野菜にしては多く含まれていますので積極的に食べたいですね。
ビタミンK(690μg)
ビタミンKには血液の凝固をサポートする働きや、カルシウムを骨に沈着させて丈夫にする作用があります。
大葉には骨を形成するカルシウム(230mg / 100g)とマグネシウム(70mg / 100g)も豊富に含まれており、骨粗鬆症への効能や骨折を予防する効果を期待できます。
カリウム
大葉は上述したカルシウムやマグネシウムなどのミネラルも豊富で、カリウムも100g当たり500mgと多く含まれています。
カリウムはナトリウムの排出を促す作用があり、高血圧予防やむくみへの効能を期待できる成分です。
ロズマリン酸
シソにはロズマリン酸というポリフェノールが含まれています。
ロズマリン酸には脂肪酸の消費を促進する作用があり、血液をサラサラにする効果があるとされる成分です。
カリウムとロズマリン酸のダブル作用で、血液の健康に対する効能を期待できます。
食物繊維
大葉には100g当たり7.3gもの食物繊維が含まれています。
野菜全般そうですが、大葉も便秘解消に有効です。
ペリルアルデヒド
シソの香りは、ペリルアルデヒドという成分によるものです。
殺菌作用が強く、防腐剤としての効能を期待できます。
お刺身のつまとしてシソの葉が用いられるのは、魚が傷むのを防いだり、臭いを抑えたりするためです。
食欲を増進する効果もあるといわれており、胃腸への効能も期待できます。
夏バテ対策に旬の大葉を食べよう
大葉には体全体の代謝を担う栄養成分が豊富に含まれており、疲労回復や食欲増進にも役立ちます。
火を通せば普通の葉物野菜と同じように食べられますし、薬味として素麵のつゆに入れるのもオススメです。
夏バテ対策に旬の大葉を食べて、暑い夏を乗り切りましょう。